話題のニュースを「ターゲットマーケティングのセグメンテーション」から読み解く
大和ハウス工業は、2021年4月29日、都心部の富裕層向けに戸建て住宅の新商品の発売を発表しました。日経新聞オンラインの記事によると、建設価格は7,000万円を超え、大和ハウス工業の中でも「最高級」に位置づけられるそうです。具体的な仕様として、木造と鉄筋コンクリート構造を組み合わせたもので、都心の限られた土地でも広々とした空間や地下室を提案するというコンセプトのようです。
大和ハウス工業では、今回、新たにデザイナーチームを発足させ、顧客の要望に合わせた設計を実現するそうです。例えば、地下室はシアタールームや音楽スタジオ、ワインの貯蔵庫など富裕層ならではの嗜好品や趣味を楽しむ空間として提案するそうです。
しかし、都心部の住宅といえばマンションが主流ではないでしょうか。なぜ、大和ハウス工業はあえてこの時期に富裕層向け戸建て住宅の発売に踏み切ったのでしょうか。
その疑問を、ターゲットマーケティングのセグメンテーションの観点で考察します。
ターゲットマーケティングとは、市場をさまざまなセグメントに区別し、これらのセグメントのいくつかを選択して集中化し、それぞれの標的市場のニーズにあった製品とマーケティング・ミックスを開発することです。
市場をさまざまなセグメントに区別することを、セグメンテーションと言います。
セグメンテーションでは、市場を地域によって分類する地理的変数、年齢や性別など客観的なデータで分類するデモグラフィック変数、ライフスタイルやパーソナリティなど主観的な要素で分類するサイコグラフィック変数、そしてニーズや購買実績などの行動変数の切り口で分類します。
以前は、20代女性、シニア層といったデモグラフィック変数が一般的でしたが、最近ではデモグラフィック変数に、サイコグラフィック変数をかけ合わせてセグメンテーションするのが一般的と言われています。
たとえばフランフランでは、創業期に、都会で一人暮らしの25歳のOL A子さんといったターゲットを想定したそうです。これは一見すると、都会(地理的変数)、一人暮らしの25歳のOL(デモグラフィック変数)で分類されているようですが、その背景には「おしゃれな暮らし」「仕事も趣味も楽しみたい」といったサイコグラフィック変数も隠されているように感じます。
今回の大和ハウスも同様だと感じます。
記事によると、大和ハウスの大友浩嗣取締役のコメントとして、「新型コロナウイルス下の外出自粛でサービスの消費ができず、富裕層は高額な不動産やブランド品などの消費が活発」と紹介されています。
つまり、大和ハウスは、単に富裕層というデモグラフィックだけではなく、その背景の「外出自粛が続くので、自宅で趣味を楽しみたい」というサイコグラフィックにも焦点を当てていることが分かります。
趣味を楽しむ空間を想定するならば、面積や同じ建物内の住民との関係などの制約があるマンションよりも、戸建ての方が適しているのは明らかです。
コロナ禍における富裕層のターゲットマーケティングという観点では、以前にこのブログでも取り上げたアンリシャルパンティエを展開するシュゼット・ホールディングスも活発に行っています。
コロナ禍の富裕層のライフスタイルの変化は、多くの経営者にとって、戦略立案上、見過ごせない環境変化と言えそうです。
おススメの記事はこちら↓
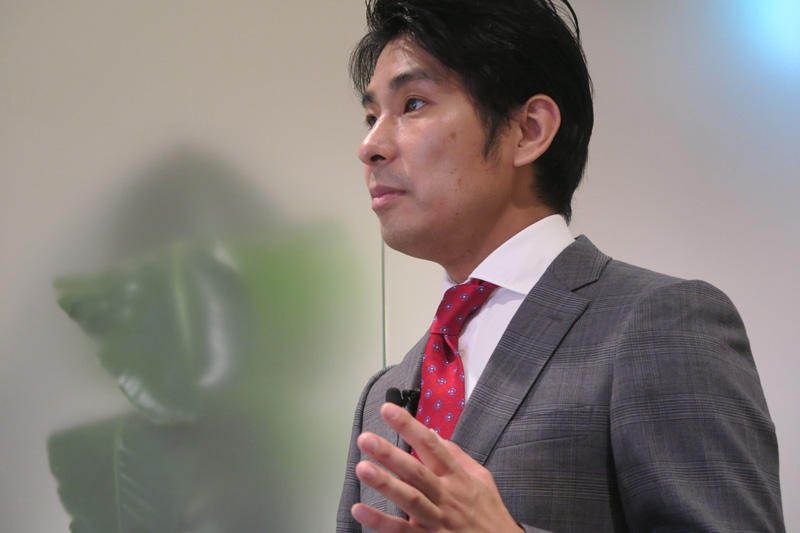
岩瀬敦智(Iwase Atsutomo)
経営コンサルタント。株式会社コンセライズ代表取締役。企業の価値を整理し、社内外にPRするコンサルティングを専門としている。特に中核人材に企業固有の価値と、経営理論を伝えることでリーダー人材の視座を高める講演や研修に定評がある。主著として、「MBAエッセンシャルズ(第3版)」共著(東洋経済新報社)、「マーケティング・リサーチ」共著(同文舘出版)など。法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科(MBAスクール)兼任講師。